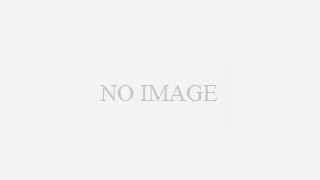 人生探訪
人生探訪 えびす(ゑびす)
えびすは日本の神で、現在では七福神の一員として日本古来の唯一(その他はインドまたは中国由来)の福の神であるとされる。今日では、狩衣姿で、右手に釣り竿を持ち、左脇に鯛を抱えてえびす顔でほほえむ姿が一般的である。どちらかというと関西地方で商売の...
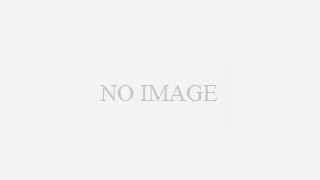 人生探訪
人生探訪 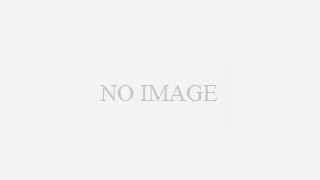 気まぐれ草子
気まぐれ草子 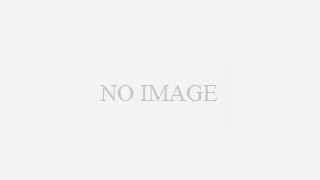 気まぐれ草子
気まぐれ草子 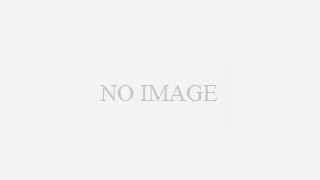 人生儀礼
人生儀礼 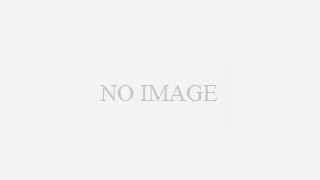 気まぐれ草子
気まぐれ草子 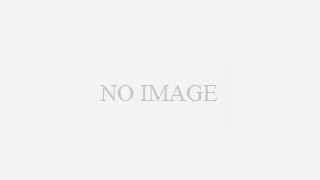 人生儀礼
人生儀礼 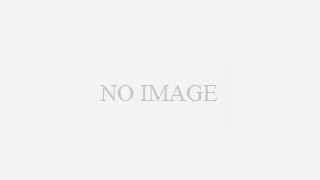 気まぐれ草子
気まぐれ草子 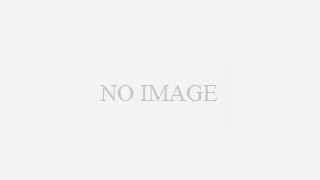 気まぐれ草子
気まぐれ草子 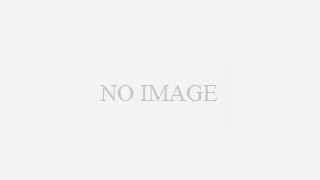 各種会報
各種会報 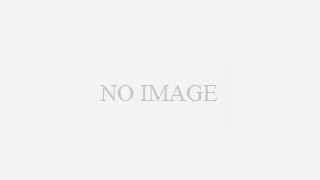 気まぐれ草子
気まぐれ草子